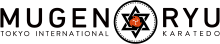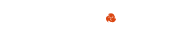――無拳流との出会いは?
今から16年くらい前、結婚と転職をして生活のベースができた頃です。
新しいことを始めて、自分を変えたいみたいな気持ちになりました。
もともとフィギアスケートなどしていて体を動かすのは好きでしたが、格闘技関係はまったく無知でした。ただ空手は型もあるし、無拳流のHPのブログを見ると楽しそうなので入会しました。37歳のことですね。
最初は蔵前道場で月1回に稽古出るくらいだったのですが、水道橋道場に行くことにしたら、女性や同じレベルの方も多く、基本を丁寧に重ねる稽古が性に合っていたのもあって週1回くらいのペースになりました。
稽古場のあるビルにはちょっと座って談笑できるようなスペースがあって、そこで稽古終わりに先生と仲間でお話するのが楽しくなっていきました。
先生のお考えや人となりを感じられ、距離感が縮まった感じがうれしかったですね。
――その後は順調にステップアップされた感じですか?
いえ、入会する前は、フルコンとか伝統派とか、空手界のこともまったくわかっていませんでしたし、月一参加のころは昇段審査を見て、その凄さに不安を覚えていました。
ただ、稽古は楽しかったので、審査は1回くらいパスしていますが必ず受けてきました。
飛び級も1回くらいしかなく、ゆっくり地道に1級づつ上がっていく間に、無拳流の空手の面白さ、奥深さを感じられて、昇段などにチャレンジできた感じです。
もともと格闘技になじみがないので、突き蹴りに慣れませんでした。
後ろ回し蹴りなど「もし当たっちゃったらどうしよう」という感じで。
そんな私でしたが、テイクダウン(投げや崩しなどの体術)があると、相手の動きや反応をみて技を出す、ということができ、それが面白かったのです。
自分から仕掛けるというより、相手との関係性の中で自分のできることを突き詰める、ということです。
これは現在のスタイルにもつながっていると思います。
――そして4段まで来られたのですね。
テイクダウンありのフルコン(旧ルール)の10人連続組手で初段、5人連続テイクダウン(体術)の対人形式の審査の弐段、1打撃無しで5回以上のテイクダウン取る10人連続組手で三段、そして基本と型の正確性を審査される四段、そして今回の新ルール(打撃寸止め・テイクダウン有)での10人組手です。
それぞれキツかったですが、チャレンジすることで確実に進歩できたことがあります。
弐段の5人連続テイクダウンではいろいろな技を習得できました。
特に私はバックステップ系はよくやるのですが、中へ入るキャッチングやカッティングは、ここで取り組むことで、少しつかむことができました。
10人組手で通算5回以上のテイクダウン取る審査では、前にガンガン出るスタイルでなくても、技を出せる、テイクダウンを取れるという確信も得られました。
基本と型はとにかく正確性を求められて厳しかったですが、やはり一つ一つの技術を見直す機会になりました。
――今回のチャレンジはいかがでしたか?
今回は、正直、先生に巻き込まれる形でした(笑)。息子もこの道場にお世話になっているのですが、彼の昇段試験も終わり、自身も50歳を過ぎ、一度指導員からも身を引き、そろそろソフトランディングかなあ、と感じていた時期でしたから。
ただ、鈴木先生や中西さん、永井さんといった一緒にやってきた皆さんがどんどん受けている。これは刺激になりました。正直、これまでの稽古の中で、新ルールは難しい、と感じていたのですが、審査という「やるしかない」状況にチャレンジさせていただいことで、この審査の10人組手の中で、間合い感覚がつかめたように感じました。皆さんの本気モードが、一つの開眼の機会を与えていただいたと思います。
改めて、この機会をいただいた山口先生、協力いただいた道場の皆さんに感謝申し上げます。
――これから無拳流とどのようになっていきたいとお感じですが?
本当にゆっくり始めて、今回のようなチャンスをたびたびいただき、16年も続けることができたのは一重に、無拳流の道場の居心地の良さ、居場所感にあると思います。ただ仲良しなだけでなく、筋を通すべき時に通していく、山口先生のご姿勢、ご方針にこれからも添っていきたいと思います。
入門者をみな、人間としてきちんと尊重する、敬意をもって稽古を一緒にする、というこの道場の美質を大事にしていきたいと思います。
私はこれから体力が上がる、ということはないでしょう。
でも、まだできることがある、と審査を通して確信しています。
このルールの中で工夫し探求できることがすごくうれしいです。
たとえば、これまで割と好きだったガードの中に空間を作って、相手に出させて取る、ということを新ルールでやれるようになりたいと思います。
一緒に頑張ってきた皆さんと、これからもご一緒し、若い世代とは交流をして、そしていつか、息子と一緒に研鑽できるようになったらいいな、と思っています。
“翔太君、辰一君”と呼んで、キッズの試合で(私が)副審させてもらっていた皆さんが、今では「先生」となるまで大きく成長してくれました。
これからも同じ無拳流という同じ空手の中で、同じ土俵で、世代を超えて多く方たちと成長し合うようになっていきたいと思います。

CATEGORY
- ADULTS CLASS BLOG (74)
- KIDS CLASS BLOG (80)
- ニュース (139)
- 動画ブログ テクニック (3)
見学・体験入門随時歓迎!
見学はもちろんのこと、入門を検討されている方であれば体験入門もお気軽に!